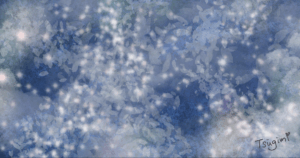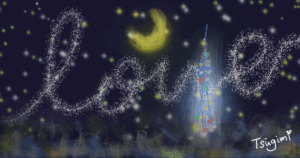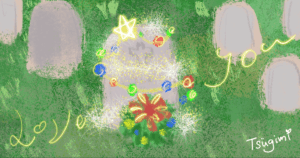強くなりたかった。
君を守るために、誰よりも強くて、優しい人になりたかった。
そのためならなんだってする覚悟があった。この命をかけて君を世界一幸せにしたいと思っていたから。
ある日、見知らぬ女が君を横目に鼻で笑って通り過ぎた。
そんな日の夜は、今度の休日に新しい口紅や洋服を選びに行こうと誘った。
もちろん、いつものラフな格好だって素敵だと伝えたら、君は少女みたいな瞳で、飛び跳ねてはしゃいでいた。
そんな笑顔が好きだった。
またある日は、見知らぬ男が君を憐れむ目で見て、悪態をついてきた。
君を悲しませるような奴は絶対に許さない。そんな時はいつだって、相手が怯むくらいの正論を突きつけて追い払った。
君の価値がわかる奴なんて、この世界にいないのかもしれない。
僕を除いては。
ある日、君はいつもよりお洒落をして楽しそうに出かけて行った。
その日も、次の日も、君は帰って来なかった。僕は心配で心配で眠れない夜を過ごした。
久しぶりに会えた君は、どこか雰囲気が違って見えた。
美しさに磨きがかかった君へのクリスマスプレゼントは、君の好きな大きな花柄のスカーフとワインを買うことに決めた。
君が綺麗になって、楽しそうにしている姿が嬉しかったから。
クリスマスの日、僕は近所の花屋で、君の好きなバラの花とかすみ草の小さな花束を作ってもらった。
君の家へ向かう足取りは軽やかだった。
君を驚かせたくて、チャイムを鳴らした後、急いでプレゼントと花束を背中に隠した。
ドアの向こうな近づく足音に心を踊らせている僕がいた。
君はきっと喜んでくれるはずだ。
ドアが開くと、部屋から楽しそうな声が響いてきた。
今日は、知り合ったばかりの男とホームパーティーの約束をしていたと告げられ、そのままドアは静かに閉まった。
楽しそうな笑い声が、冷たい空気に響き渡る。
足元に散らばった、赤い花びらは、僕が吐き出した血のようだった。
冷たい頬を伝う生暖かい雫は、僕が生きていることを主張しているみたいだった。
たぶん、ぼくはここに立っている。
たぶん、ぼくは今泣いている。
たぶん、もうここはぼくの、いえじゃなくなった。
ぼくの足元は、少しずつ白く色が変わっていた。
そうだ、今日はクリスマスなんだ。
ぼくは、今日みんなでケーキを食べるのを楽しみにしていた。
大好きなチョコレートのプレートは、じゃんけんに勝って絶対食べるんだって決めていた。
そんな景色も、いつの間にか真っ白な雪に包まれて、何もなかったみたいに、町は綺麗にラッピングされていた。
後ろを振り返ると、小さな足跡だけが付いて来てくれていた。君だけはいつもぼくの親友だよ。
踏みしめる足は、冷え切って感覚が無くなっていた。
ぼくが大きくなったら、もっと強くなったら、またママは笑ってくれるかな。
ぎゅっと手を握りしめて空を見上げた。
*この物語は、2025年12月10日に note と X に投稿したものを転記したものです。