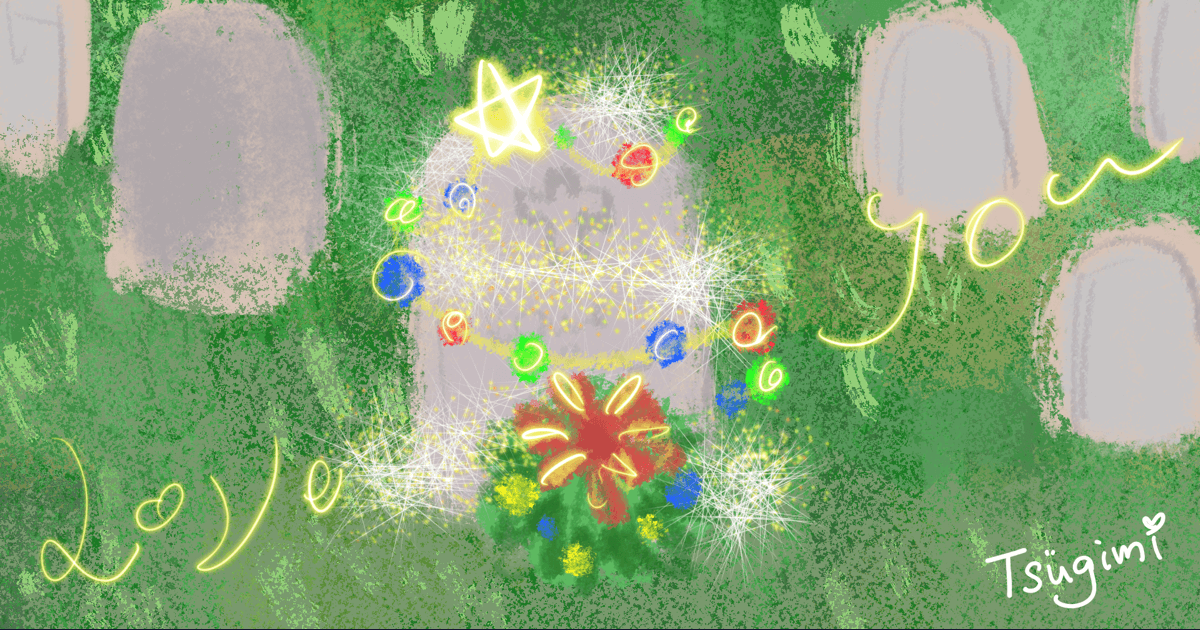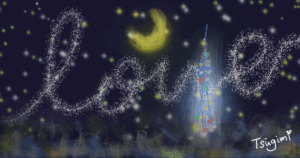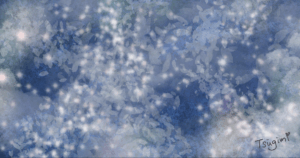一日の終わりにはいつも、冷たい貴方の頬に触れながら問いかける。
「ねぇ、あなたなら今日のこの道をどう選んだ?」
あなたはこちらを見つめたまま、何も答えない。
私はまだ、しっかりとした自信を持てずにいた。
あなたが一緒に戦ってくれていたあの日が、随分昔のことのように感じる。
私たちはいつでも最強の相棒だった。
背中を任せられる相棒を失った私は、毎晩こうして不安に押し潰されそうになっては、なんとか堪えて生き延びているだけだった。
誰かの命を救うことに、何の意味があるのだろう。
一番大切なあなたという命を失って、それでもなお、誰かの守ることの意味など、どこにも見当たらなかった。
ただ、涙が頬を伝って床に落ちていくのを見つめてるのが精一杯。
それなのに、あなたは私を抱きしめてはくれないし、慰めてもくれずに、ただ天井を見つめ続けているだけ。
私がこの部屋に居られるのは、せいぜい30分が限界だ。
私の指先は温度を失い、白い息がまつ毛を凍らせていく。
この地下室で、あなたに触れ、あなたの存在を確かめられる。それだけが私に生きる意味を与えてくれていた。
「クリスマスには、いつもみたいに一緒にパーティーをしようか」
そう呟くと、あなたの瞳が頷いたように見えた。
外に出るたびに、浮かれたクリスマスの空気が胸に刺さり続けていた。
あなたのいないクリスマスなんて、何の意味も無いと感じていたから。
何度も拭った誰も知らない私の涙は、いつの間にか空を舞い、街頭に照らされてキラキラと輝いていた。
からっぽになってしまった私の毎日にも、あなたの優しさが降り注いでいるみたいだった。
あなたとの本当の別れを決めた日、私はようやくこの世界に戻って来れたのかもしれない。
あなたが私に残してくれた最後のプレゼントは、
あなたのいないこの世界をじっくり味わい尽くす、この時間だと気付いたから。
*この物語は、2025年12月13日に note と X に投稿したものを転記したものです。